-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
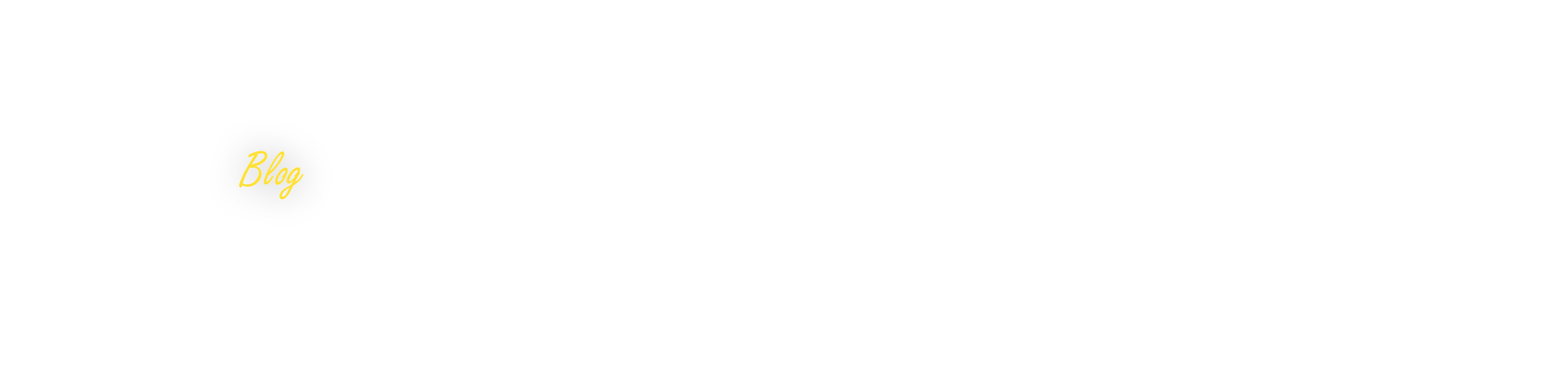
皆さんこんにちは!
合同会社HENT、更新担当の中西です。
ホテル清掃は、「見えない仕事」かもしれません。
しかしその仕事のクオリティが、宿泊客の満足度を左右することは言うまでもありません。
今回は、実際にホテル清掃の現場で日々守られている**“鉄則”=プロの心得**を、具体的な行動や考え方を交えてご紹介します。
ホテル清掃の基本は「視覚的な清潔感」ですが、本当にプロが意識しているのは**“見えない汚れ”**です。
リモコンやスイッチ類など、手が触れる場所の除菌
枕カバー・シーツの裏側、ベッド下など“死角”の清掃
トイレの便座裏・ドアノブなどに重点チェック
「お客様は気づかなくても、私たちは気づいている」
この意識が、**“安心できる清潔さ”**をつくります。
ホテル清掃は、**「時間との戦い」**でもあります。
チェックアウトからチェックインまでの限られた時間(例:11時~14時)
フロアごと・部屋ごとに割り振られる清掃枠
急なアーリーチェックインや延長にも対応
その中で大切なのが、「手を抜かずに、時間通りに仕上げる」こと。
マニュアルに頼りすぎず、効率と品質をどう両立するかが、プロの腕の見せどころです。
清掃スタッフは、直接お客様と接する機会は少ないかもしれません。
しかし、部屋に入った瞬間に伝わるのが「清掃から感じるおもてなし」です。
ベッドメイクのシワひとつない仕上がり
洗面台の鏡がピカピカに磨かれている安心感
アメニティの並べ方やタオルの折り方から伝わる“気配り”
これらの積み重ねが、「心地よかった、また来たい」という気持ちにつながります。
ホテル清掃では、ときに以下のようなトラブルにも遭遇します:
壊れた備品・シミのあるシーツの発見
宿泊者の忘れ物(スマホ、財布、貴金属など)
異臭・液体漏れなどの緊急対応
こうした際に、「黙って放置しない」「上司にすぐ報告」「記録を残す」ことが徹底されている現場こそ、信頼されるホテル清掃のプロチームです。
意外に見落とされがちですが、自分自身が清潔であることも大切な鉄則です。
清掃ユニフォームの洗濯と整備
マスク・手袋・靴の状態確認
作業前の手洗い・消毒の徹底
「清潔を提供するには、自分も清潔であるべき」——これはプロとしての最低限の意識です。
ホテル清掃の鉄則は、“ただの掃除”では終わらせないプロ意識の結晶です。
裏方であっても、お客様の快適と笑顔を思って働くこと。
それが、清掃スタッフの誇りであり、ホテルという“おもてなし産業”の本質です。
これからも清掃という仕事は、進化し続けます。
AIやロボットに一部は任せられても、「人の心を感じる清掃」は、人にしかできません。
私たちは、今日もまた一室一室に心を込めて、「最高の空間」を仕上げています。
次回もお楽しみに!
![]()
皆さんこんにちは!
合同会社HENT、更新担当の中西です。
旅行や出張で宿泊する際、宿泊客が最初に体感するのは「清潔感」です。
その第一印象を決めるのが、私たち清掃スタッフの仕事。
しかしこの「ホテル清掃」という仕事が、いつ・どのように誕生し、どのように進化してきたかを知っている人は少ないのではないでしょうか?
今回は、ホテル清掃の歴史にスポットを当て、サービス業の裏方として進化し続けてきたこの職種の足跡を振り返ります。
ホテルという概念が日本に根付いたのは、明治時代以降。
横浜や神戸、東京などに西洋人向けの宿泊施設ができたのが始まりです。
初期のホテルは「洋館」で、家具も備え付け、使用人が清掃を担当
明治・大正期には、女中や下働きが床磨きや寝具の手洗いを担っていた
この時代の清掃は、**「雇われた者が黙ってこなす作業」**という扱いでしたが、サービス意識の萌芽はすでに生まれていました。
戦後、日本経済の復興とともに観光業が成長。
修学旅行・社員旅行などの団体旅行が流行し、ビジネスホテルや観光ホテルが全国に展開されます。
ホテルの客室数が拡大 → 清掃作業の“チーム化”
客室清掃・浴場清掃・館内巡回などの業務が細分化
「清掃係」という専門職がホテル内に設置され始める
この時代、清掃スタッフは表に出ることが少なく、裏方のプロフェッショナルとして“縁の下の力持ち”的存在として定着していきます。
バブル期以降、ホテルは単なる宿泊施設ではなく「滞在体験の場」へと変化します。
その中で、清掃の重要性も再認識されるようになります。
清掃専門会社が登場し、外注・委託が主流に
マニュアル化・効率化が進み、作業スピードと品質の両立が求められる
外国人観光客の増加により「国際水準の清潔感」が基準に
また、ホテルの格付け(星の数)やレビューサイトでも、清掃の評価が重要視されるようになり、清掃業務は「おもてなしの第一段階」として注目されるようになったのです。
2020年以降、世界を揺るがした新型コロナウイルス感染症。
ホテル清掃業界も例外ではなく、大きな変化を迫られました。
除菌・抗菌清掃の導入(次亜塩素酸水・アルコール・UVライトなど)
客室内の「触れる部分」を重点的に管理する“接触点清掃”
ベッドメイク・タオル交換・アメニティ補充の一部省略(エコ清掃)
この時期から、「清掃は安全を守る仕事」という認識が広がり、清掃スタッフが“衛生の守り手”として再評価される契機となりました。
ホテル清掃の歴史は、常に「お客様の快適」を支える裏側にありました。
単なる作業ではなく、文化・時代・社会の変化とともに進化してきたこの職業は、
今や**“プロのおもてなし業”**としての地位を確立しつつあります。
次回の記事では、そんな清掃スタッフが日々現場で大切にしている「鉄則」について、実例を交えて深掘りしていきます。
次回もお楽しみに!
![]()